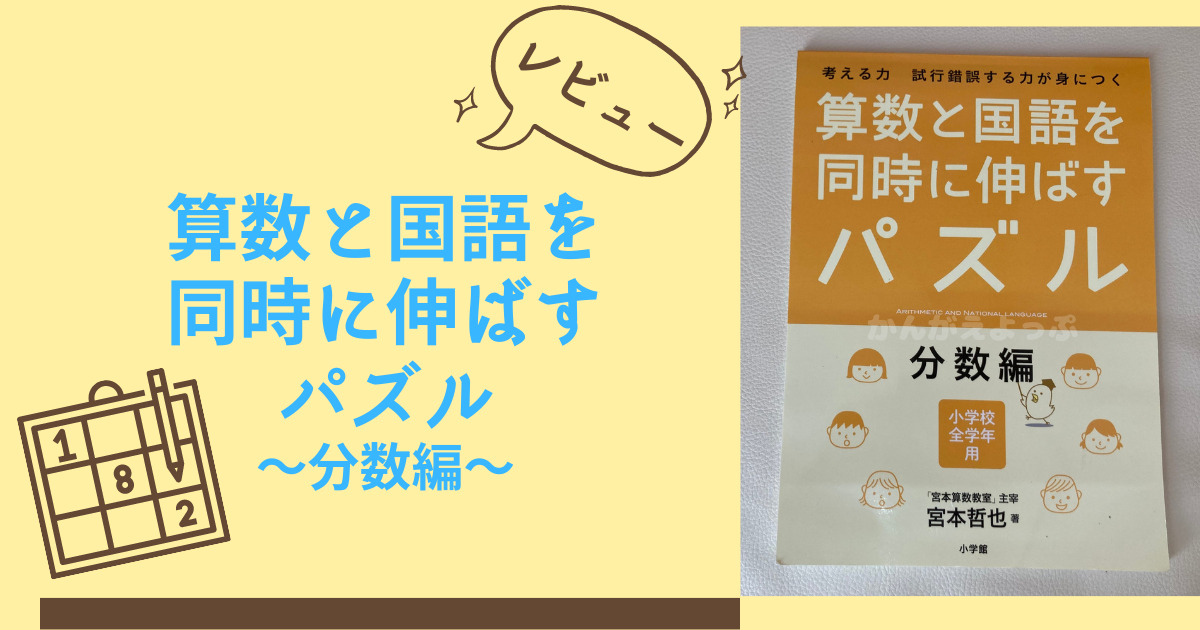小学校の算数では分数を2年生で少し触れ始めて、3年生では本格的に学習します。
この分数が算数におけるつまずきポイントの一つなんです。
分数の何が難しいって、「概念」自体が難しい!
「〇分の1」は生活の中で出てきやすいので、考えやすいですよね。

私も小学生の頃、ピザやケーキの切り方で考えました。
でもその先は…「分数の概念」がわからないと難しい。
この「分数の概念」さえしっかり理解できれば、複雑な問題になっても解くことができます。
「分数の概念」を理解できて、定着させることができる教材はないかと探しました。
見つけて購入したのが『算数と国語を同時に伸ばすパズル 分数編』です。
この問題集を使うと、線分図をマスターできますよ。
他の『算数と国語を同時に伸ばすパズル』シリーズはすでに愛用中ですが、
「分数編」もとても良かったので、詳しくご紹介しますね。
算数と国語を同時に伸ばすパズル 分数編 (小学館)
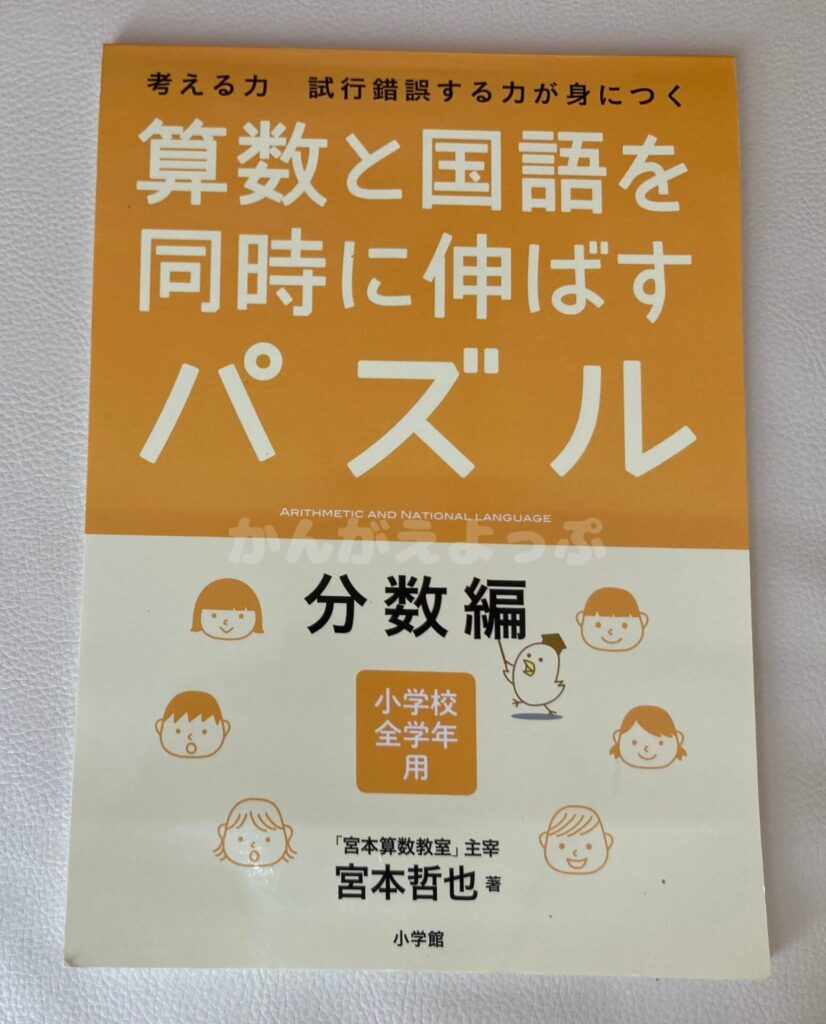
『考える力 試行錯誤する力が身につく
算数と国語を同時に伸ばすパズル 分数編』
著者:宮本哲也(「宮本算数教室」主宰)
出版社:小学館
定価:660円(税込)
この問題集を選んだ理由
- 分数の概念が理解できる問題集
- 文章から線分図が書けるようになる
- 問題量が多すぎない ⇒ 一冊やり遂げられて自信が付く
- 難易度が上がる ⇒ 最初は簡単でも自然と難しい問題も解けるようになり自信が付く
一番の決め手は『線分図を書けるようになる』というところ。
分数の問題は、正確に線分図が書けるようにさえなれば複雑な問題でも解くことができます。

この問題集は文章題なのですが、線分図を理解できるようになれば、通分や計算の理解も進みますよ。
『算数と国語を同時に伸ばすパズル』シリーズなので、ほかのシリーズ同様、条件がそれぞれ書かれているので正確に読み取る必要があります。
考える力をつけるために、しっかりと考えさせる問題になっていますよ。
算数と国語、線分図がマスターできる方法とは?
問題の形式としては、表は推理パズル、裏はかけ算ブロックです。
推理パズルは、問題文を読んで、条件から正解を推理するパズルです。
例えば「〇が△㎝あります」「◆分の■あげるね」のような条件文があり、そこから残り何㎝かというような問題です。
分数の分野ではよく見る問題ですよね。
まずは正確に情報を読み取り、線分図に書き込みながら整理します。
条件を読み取る⇒整理する⇒線分図にまとめる
正確に線分図が書ければ、おのずと答えが導き出されますよ。
「分数編」は一冊しかありません。
なので、その中で難易度が上がっていきます。始めこそ、例に出したような問題ですが、だんだん条件も複雑になってきます。
最後の方は、一題の条件文に対して、問題が3問ついています。

難しくなってきますが、そこまで解けるようになれば、線分図マスター !
そして「分数の概念」についてしっかりと理解できていると思いますよ。
そして裏面のかけ算ブロックは、一般的な「数独」や「ナンプレ」に似ていますが、枠の取り方を少し複雑にして、さらにかけ算が必要なパズルです。
4×4のマスにそれぞれ1~4の数字が入ります。
4×4マスの中は枠で分けられていて、枠の中は決められたかけ算の答えになるように数字を入れていきます。
宮本哲也先生が開いている算数教室。
東京にしか教室がなく先着順なので、すぐ定員に達して順番待ちになるほどの人気ぶり。
無試験、先着順にもかかわらず、最難関中学へ生徒の80%が進学する実績を持つ。
シリーズ
『算数と国語を同時に伸ばす』シリーズは全部で6種類あります。
- 方法(保護者向け)
- パズル 入門編(小学校全学年用)
- パズル 初級編(小学校全学年用)
- パズル 中級編(小学校全学年用)
- パズル 上級編(小学校全学年用)
- パズル 分数編(小学校全学年用) ←この記事
算数と国語を同時に伸ばすパズル入門編も使っていますよ。
算数と国語を同時に伸ばすパズル分数編の中の様子
- B5サイズの冊子
- 余白、解答欄ともに広めで書き込みやすい
- 漢字・カタカナ使用あり ⇒ 全漢字にフリガナあり
カタカナにはフリガナがありませんが、一緒にイラストが描いてあるのでわからないということはないと思います。
かけ算ブロック
かけ算ブロックの方は、「数独」とは少し違ったものです。
いくつかの枠で分けられた4×4マスに1~4の数字を入れていきます。
枠の中は決められたかけ算の答えになるようにしますよ。
難易度が上がってくるとかけ算が難しくなってきます。
具体的には、目指す答えが一桁、二桁だったものが、最後の方は三桁も。
計算としては2桁×1桁が必要になります。

そんなかけ算できないから無理!ではなく九九さえできれば、工夫して計算することは出来ますよ。
この考えて工夫力をつけていきたいですね。
パズルの難易度
パズルは難易度別で出版されていますが、1冊の中でも、初級・中級・上級に分かれていて、だんだん難易度が上がります。
分数編で、初級7問(推理パズルは8問)、中級8問、上級9問と全部で24(推理パズルのみ25)問。
※分数編-初級1問目は表が推理パズル、裏はかけ算ブロックの例題になっています。推理パズルの例題は1問目の前のページに掲載されています。

各級が終わると級位認定証もついていますよ。
ぜひ名前を書いてあげてください。とても喜びますよ。
感想とメリットデメリット
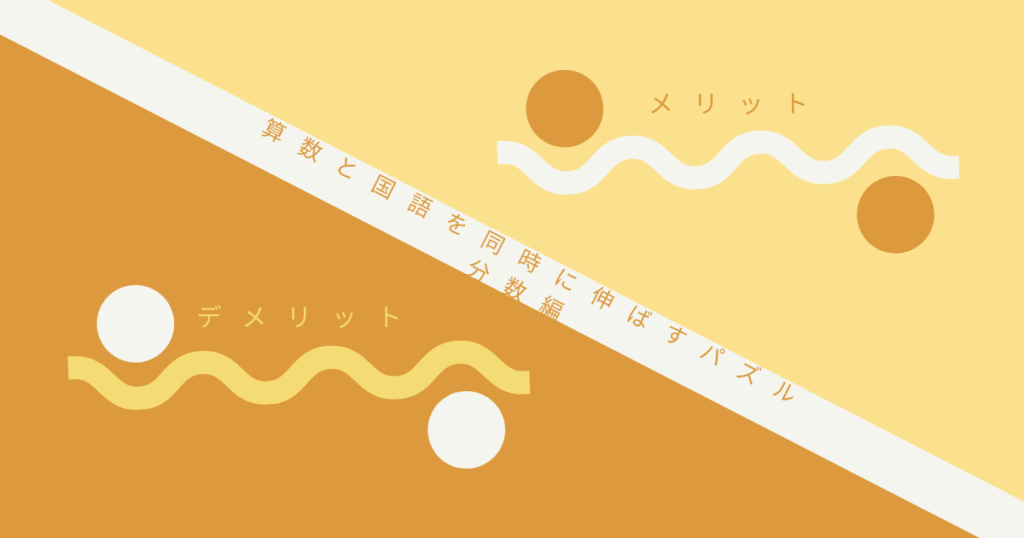
実際に問題集を使ってみた感想と、メリットデメリットについてまとめました。
実際に使用してみた感想
学校で少し分数をやり始めてから購入しました。
推理パズルの方は、線分図に書き込むのを面倒と感じているようでしたが、何回もやっているうちにスムーズにできるようになってきました。
ただ、難易度が上がり、複雑になってくると悩んでいますよ。

悩んで考えることで、思考力はついてきます。
購入してよかったなと思いました。
『算数と国語を同時に伸ばすパズル 入門編』の次に購入したので、かけ算ブロックに戸惑っていました。
「入門編」のときは、数字ブロックだったので、推理パズルよりも数字ブロックを好んでいましたが、今度は逆。
かけ算ブロックに戸惑ってしまい、なかなか進みません。
たし算ブロックやひき算ブロックなどの計算ブロックに慣れてからのが良かったかなと思いました。
たし算ブロックの「国語を同時に伸ばすパズル 初級編」も購入したので、計算ブロックにも慣れていくかなと思います。
メリット

- 反復練習で線分図をマスターし、分数の概念が理解できるようになる
- かけ算ブロックで考える力アップ
- 似たような問題だが、難易度が上がっていくため理解が深まる
- 条件を正確に読みよる必要があるが、会話形式になっているので読み取りやすい
デメリット

- 似たような問題の繰り返しで、バリエーションがあるわけではない(反復練習)
- 問題数は多くないので、コスパが悪いといわれることがある
- 一冊で完結するため、最初の問題と最後の問題ではだいぶレベルが違う
こんな人はオススメです
- 分数の考え方をマスターしたい人
- 線分図が書けるようになりたい人
- パズルが好きな人

問題数は少ないですが、これだけ同じことを繰り返せば理解はできるはず!
物足りない場合は、ほかの教材でもっと演習するのも手ですね。
まとめ -線分図がマスターできますよ-
推理パズルとかけ算ブロックが表裏に1題ずつ載っています。
推理パズルで条件を
正確に読み取る → 整理する → 線分図にまとめる
という作業ができるようになります。
線分図にまとめることができるようになると、分数の概念について理解できますよ。
分数の概念が理解できると、分数の計算になっても、ルールに沿ってなんとなく解くのではなく、理解したうえで解くことができるようになるので「うわー解き方忘れたから解けない!」ということは減っていくと思います。
かけ算ブロックで、「集中力」「思考力」「試行錯誤する力」などが身に付きます。
最初は戸惑いますが、論理的に解いていくほかありません。
根気がいりますが続けているうちに、だんだん根拠のある数字を入れられるようになってきますよ。
分数が始まったばかりの人、分数でちょっとつまずいている人におすすめの問題集です。
ぜひ取り入れていてはいかがでしょうか。